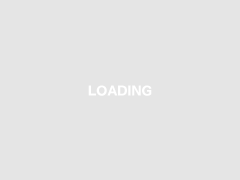イベント
“俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/001.jpg) |
本講演は,対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」(PC / PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Switch2)の,プレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」を通して,プレイヤー同士の対戦を元にしたAIの作成工程や,ゲームへの理解を深めさせ,次回のプレイへとつなげる仕組みなどを紹介するものだ。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/002.jpg) |
安原氏はまず,Vライバル(まねもんくん)の目的が「同じ強さの相手と毎日戦えるようにするため」であると語った。理由はシンプルに,対戦ゲームにおいて「同じ強さの相手と戦うのは面白い」からだ。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/003.jpg) |
ストリートファイター6には,ある程度同じ強さの人と対戦できる「ランクマッチ」が用意されている。しかし,誰しもがいきなり対人戦に乗り気になれるかというと,そうではない。
「ワールドツアー」や「アーケードモード」など,初心者が対人戦に至るまでをサポートするさまざまなモードも存在するが,安原氏はランクマッチへの挑戦には大きな崖があると感じたそうだ。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/004.jpg) |
その崖を越えるためには,2つのハードルが存在すると安原氏は続ける。
まず1つ目は,ストリートファイター6にさまざまなシステムや技術があるという「技術的ハードル」だ。しかし,最初からすべてを覚えられる人などいないので,これは先述の「同じ強さの相手との対戦」を行えば,段々と自身のレベルにあった技術を身につけられる。
次に,自分がしっかり動けているかどうか分からず,人によっては対戦相手に申し訳なさを感じてしまうといった「心理的ハードル」だ。これは,対戦後に何ができていたかを明確にして成長を実感させたり,逆に何ができていなかったかを教えて成長のきっかけを与えたりすることで,ハードルを下げられるという。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/005.jpg) |
そのためにVライバルに用意された機能が,各ランク別のAIによる「ライバルとの実践」と,対戦後にその内容を評価する「肯定とアドバイス」だ。
続けて,Vライバルで各ランク帯のプレイヤーの強さを再現するために,いったいどのような手順をとっていたのか,AIの構築について詳しい解説がなされた。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/006.jpg) |
まずはじめに,日々世界中で行われるオンライン対戦のリプレイ(キーの入力情報)から,Vライバルのための学習データを作成する。そこには,特定の行動をとったタイミングの,さまざまな情報をまとめた「スナップショット」と呼ばれるデータが,大量にまとめられている。
これにより,AIが「このシチュエーションではこの行動をとっている」という学習を行えるわけだ。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/007.jpg) |
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/008.jpg) |
ここで,実際にAIが学習していく様子を動画にまとめたものが紹介された。
プレイヤーとAIが対戦するという内容で,1ラウンド目はプレイヤー側がずっと飛び道具を打ち続け,AIは何もせずそのまま敗北した。
次のラウンドでは,さきほどプレイヤーが見せた行動を学習したAIが,同じように飛び道具を打ち続けるようになった。しかしプレイヤー側はそれに対して,ジャンプ攻撃による飛び道具への対策を行う。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/009.jpg) |
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/010.jpg) |
すると,AIはプレイヤーが飛び道具を撃つタイミングでジャンプをしてくるようになった。今度はプレイヤーがその対策で対空攻撃を行い,これも覚えさせる。こうしてどんどん学習を進めたAIは,わずか数戦後にはさまざまな選択肢を取るようになっていた。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/011.jpg) |
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/012.jpg) |
スナップショットには「キャラクターのアクション」「空中かどうか」「ラウンド状況」「ゲージ状況」「弾の種類と発射されてからの時間」「キャラクターの位置」「相手との距離」という,7つの項目を数値化したものが記録されている。
VライバルのAIは,それらの数値から,現在のシチュエーションに近い数値のスナップショットを選択し,そのキー入力を再生しているそうだ。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/013.jpg) |
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/014.jpg) |
なお本機能は,対空などの反応が遅れたり,コンボ選択を間違えてしまったりと,プレイヤーが起こしがちな“うっかりミス”も再現することで,「強さ」よりも「らしさ」を重視したつくりになっているという。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/015.jpg) |
例えば,AIが「強パンチがヒットしてからコンボに入る」というスナップショットを対戦で再生したとする。そこでもし強パンチがガードされてしまった場合,その時点でAIは「ガードされた時」のスナップショットへと差し替えを行う。
しかし,ヒットとガードの確認を100%行えるプレイヤーはまずいない。そのため,ガードされているのにそのままコンボ技を発動してしまったり,逆にヒットしているのにガードされた時の技を入れ込んだりしている「人間らしいデータ」も,スナップショットには含まれているという。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/016.jpg) |
このようにVライバルは,実際の対戦で発生したシチュエーションを限りなく再現する,すべてのプレイヤーの分身ともいえる存在であることが説明された。これならば,いわゆるCPU戦で発生するような「理解不能な行動」や「超反応」といった人間らしさのない動きは,かなり少なくなるだろう。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/017.jpg) |
セッションの後半では,2つ目のハードル「心理的ハードル」を越えるために,プレイヤーがゲームを楽しみながら上達できる,対戦後の評価やアドバイスのシステムについて解説が行われた。
安原氏によると,このアドバイス機能は,勝ち負けよりも「昨日の自分より強くなれたか」を伝えるための機能であるという。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/018.jpg) |
例えば,ストリートファイター6には,相手の攻撃を受け止めながら反撃する「ドライブインパクト」という技がある。さらに,相手のインパクト発動中にインパクトを発動すると,特殊な演出とともに相手が無防備な状態になる。要するに,カウンターが強力な技だ。
しかし,ドライブインパクトは相手の技を受け止められるだけの体力が残っていないと,そのまま体力が尽きて負けてしまう。安原氏は実例として,そんなインパクト返しに成功したものの,体力が足りず負けてしまったという場面を挙げ,試合に負けてしまったとしても,できていることをちゃんと「えらい」と伝えたいと,本機能に込めた想いを語った。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/019.jpg) |
評価までの流れとしては,Vライバルと対戦をすると,その内容を分析したAIが,対戦でできていたことを褒めてくれたり,逆にできなかったことへのアドバイスをくれたりする。さらにNPCからプレイヤーの総合的な評価を聞けたり,クリアするとスタンプなどの報酬がもらえる課題の提案をしてくれたりする。
この,実力の近い相手(Vライバル)との対戦,その後のアドバイス,課題の提案,が1つのサイクルになっており,課題に挑戦するために再び対戦を行い,またアドバイスをもらうという流れを繰り返すことで,自然と実力が身についていくというわけだ。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/020.jpg) |
では,対戦の内容はどうやって評価しているのだろうか。AIのアドバイスは,試合中の行動をチェックして提供されるわけだが,そのチェック項目は「ガード」「対空」「崩し」「反撃」「コンボ」「ゲージ」「システム活用」の7つであるという。
具体的には,対戦中にどれだけの精度で防御や攻撃を行えたか,相手のスキにしっかりと反撃を入れられているか,ゲージやキャラの固有システムしっかり使えているか,ストリートファイター6のシステム(ドライブインパクトなど)をちゃんと活用できているかなどで,格闘ゲームの基本だけでなく,ストリートファイター6らしい立ち回りも評価対象になっているようだ。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/021.jpg) |
ここで,実際の対戦からアドバイスまでの流れを動画にまとめたものも紹介された。コンボをつないだ瞬間や起き攻めで技を重ねた瞬間など,技術が求められる行動や,立ち回りとして強い行動を取ると,最後にAIがそれらをちゃんと指摘して,褒めてくれる様子が確認できた。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/022.jpg) |
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/023.jpg) |
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/024.jpg) |
このように,プレイヤーの長所を重点的に褒めることで,勝ち負けにかかわらず,自分のプレイに向き合って成長していってほしいと,安原氏は述べた。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/025.jpg) |
続いて,Vライバルのデータの更新など,ネットワーク関連の現状が簡単に紹介された。
Vライバルは,キャラクターとランク,さらに操作タイプ,それらすべての組み合わせが存在する。また,対戦するキャラクターごとに戦い方を変えなければならず,それをかけ合わせた組み合わせは5万通り以上にもなるという。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/026.jpg) |
これを毎日更新するのはとてもできないので,今のところは1週間に1回程度のペースで更新しているそうだ。なお,初期のころは1つの組み合わせのデータを作成するのに1分ほどかかっていたという。現在は少し短縮されたものの,やはりすぐに終わる量ではないとのことだ。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/027.jpg) |
最後に,Vライバルを応用することで生まれた,さまざまなコンテンツが紹介された。
1つ目は「自分のVライバルとの対戦」だ。これは,Vライバルの学習対象を,自分の対戦データに絞ることで実現されている。現実では不可能な対戦カードというだけでなく,まったく同じ行動が発生したり,自分の弱点を突いてみたりと,なかなか味わい深い体験になっているという。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/028.jpg) |
2つ目は「特別なVライバル」だ。これは世界中のプレイヤーの誰かと,擬似的に対戦が行えるという機能である。その例として,有名な格ゲーマーであり,現在ストリートファイター6の開発に携っているヲシゲ氏を再現したVライバルが紹介された。
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/029.jpg) |
安原氏は,Vライバルの開発により,対人戦へのハードルを新しい体験に変えられただけでなく,その応用により新しい遊びの幅も広げられたとし,多くの対戦データの元となっているプレイヤーたち,そして開発に携わった各スタッフへと謝辞を述べ,講演を締めくくった。
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/030.jpg) |
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/031.jpg) |
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / “俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/032.jpg) |
「ストリートファイター6」公式サイト
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 ストリートファイター6
ストリートファイター6
- 関連タイトル:
 ストリートファイター6
ストリートファイター6
- 関連タイトル:
 ストリートファイター6
ストリートファイター6
- 関連タイトル:
 ストリートファイター6
ストリートファイター6
- 関連タイトル:
 ストリートファイター6
ストリートファイター6
- この記事のURL:
キーワード
- PC
- PS5
- Xbox Series X|S
- Nintendo Switch 2
- PC:ストリートファイター6
- アクション
- CERO C:15歳以上対象
- カプコン
- プレイ人数:1〜2人
- 格闘
- 対戦プレイ
- PS5:ストリートファイター6
- Xbox Series X|S:ストリートファイター6
- PS4:ストリートファイター6
- PS4
- Nintendo Switch 2:ストリートファイター6
- イベント
- CEDEC 2025
- 編集部:Igarashi
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM



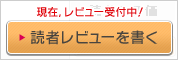
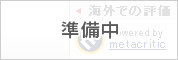


![“俺と同じ強さのやつに毎日会いに行く”を実現するために。「スト6」のプレイヤーを模したAI「Vライバル(まねもんくん)」ができるまで[CEDEC 2025]](/games/635/G063504/20250801054/TN/033.jpg)