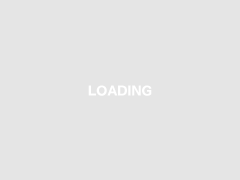インタビュー
[インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/003.jpg) |
本作は,ウォーキングシミュレータ「NOSTALGIC TRAIN」や,パズルアドベンチャー「最涯(さいはて)の列車」を制作した畳部屋氏の3作目で,中世風の世界を舞台に,育ての親元を離れた主人公が,無名の浪人として世界を旅するというシミュレーションゲームとなる。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/002.jpg) |
そして,旅の目的になるのは,世界の崩壊を止めること……急に壮大な話になったが,正確には崩壊に向かう世界で,どうにかしてバランスを保てるように行動しなければならないらしい。しかし,その動き方次第ではプレイヤー自身が世界の崩壊を早めてしまうというのだ。
そんな本作だが,画面を見るといわゆるリアルタイムストラテジーのように思えるグラフィックスである。しかし,実際にプレイしてみると,主人公の動きが止まっていると世界の時間も止まり,プレイヤーが主人公を何か行動させると,NPCを含めた世界が動く仕組みとなっていた。
ただ,この主人公,荷物はあまり持てないし,食料がなくなる(わりと早い)と体力が減って,いずれは倒れてしまう(近くの砦に運ばれる)。目的の場所に行くのも,そこそこに大変だ。
ブースにあるパンフレットを見ると,プレイヤー自身は街や城,村の探索から,国や商会,盗賊などの勢力に加入しての仕事,自身の国を立てての統治まで,かなり自由度の高いプレイが可能となっているようなのだが……正直なところ,BitSummit会場で短時間,デモ版をプレイしただけでは把握しきれなかった。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/001.jpg) |
そこで,会場に来ていた畳部屋氏に,本作がどのようなゲームなのかを聞いた。また,畳部屋氏といえばCD PROJEKT REDで開発に携わっていたことも知られる人物であり,個人でインディーゲームを制作するモチベーションや,その苦労についても聞いてみた。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/004.jpg) |
最適解はない? プレイヤーを悩ませるギリギリを狙ったバランス調整
4Gamer:
本日は,よろしくお願いします。畳部屋さんが最初に制作を発表されたゲームは,「NOSTALGIC TRAIN」という日本の懐かしい風景を背景としたタイトルで,発表当時にUnreal Engine 4によるリアルで,美しいグラフィックスが話題になっていました。
続く,2作目も列車をテーマにしていたかと思うのですが,それが今回の「歴史の終わり」では,ガラッと作風が変わっていたので,そのキッカケが気になっていました。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/025.jpg) |
私はプログラマではなかったので,Unreal Engineを触り始めたときは,どうロジックを組んでいるのか分かっていなかったんです。
ですから,最初のうちは,自分が作りたいもののなかで作れるものをということで,ノベル系ウォーキングシム的なものを作ったり,次にパズルアドベンチャーを作ったりして,ちょっとずつブループリント(※Unreal Engineで視覚的にゲームを制作できるシステム)の仕組みに慣れていきました。
そうして,知識が詰まってきたので,昔から作りたかった,こういうゲームが世の中にあればいいのにと思っていたものを,3作目にしてついに取り掛かれたといった感じです。
4Gamer:
もともとプログラマではなかったんですね。以前はCD PROJEKT REDで制作に携わっていたそうですが,当時はどのようなお仕事を?
畳部屋氏:
「サイバーパンク2077」だったり,「マフィア3」だったりの3D背景を作っていました。ですので,オープンワールドの街を,どうやって作るかみたいなことを,ひたすら考えていましたね。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/005.jpg) |
4Gamer:
それが,これまでのインディーゲーム作品につながっている,と。
畳部屋氏:
そうですね。オープンワールドゲームを作るのは,すごくたくさんの要素をどうやってうまく組み合わせるか,みたいなところがあります。ですから,シミュレーションゲームを作るというのは,オープンワールドゲームがどういう仕組みなのかを考えるのと,近いところがあるんです。
4Gamer:
シミュレーションゲームを作るうえで,バランス調整にもその経験は生かされたのでしょうか。
畳部屋氏:
バランス調整は,すごく苦労しています(笑)。こういうストラテジーゲームは,エンディングを1回見たら終わりではありません。例えばSteamにある評判のいいストラテジーゲームは,プレイ時間を300時間とか,1000時間とか書いているプレイヤーがいるじゃないですか。「歴史の終わり」も,それだけ遊んでも耐えられるようなゲームにしたいんです。
4Gamer:
自由度が高く,何度も遊べる,つまり毎回違った体験ができるゲームとなると,そうとうにバランスが難しそうです。
畳部屋氏:
ええ。ですから,どのようにバランスを調整するかは,すごく考えています。
例えば,パラメータをエクセルで大量に計算して,どういう可能性で数値が上がるのか,もしくは下がっていくとしたらどういう範囲になるのか。この範囲だったら,プレイヤーのお金がギリギリになって苦労するだろうから,ゲームとして面白くなるだろう……みたいなことを考えて,パラメータを調整して,決定して,といったことをひたすらやっています。
もちろん,オープンワールドゲームの街を作るときは,そういうパラメータ調整をするわけではありません。
ただ,例えば家を1個作るとしたら,それがメモリ全体で,どれくらいのパフォーマンス負荷になるのかを考えながら作ります。そのときの,たくさんの数字を見て最適な予想を立てて調整するというのは,このバランス調整に近いかもしれないですね。
4Gamer:
そういったバランス調整には,コツだとか,理念といったものがあるのでしょうか。
畳部屋氏:
1作目で制作を学びつつ,試行錯誤しながらなので,コツといえるほどではないのですが,バランス調整は常に,こっちを立てれば,あっちが立たずというものです。遊ぶ人にとっても,この状況が発生するようにしたいと思っているんです。
例えば,プレイヤーは傭兵を雇えますが,荷物をたくさん運べる人物を雇えば,交易するときにたくさんの交易品を運べるので,お金を稼ぎやすくなります。
一方,街や村などで包囲戦をするときは,食料をたくさん持たせておかないと(キャラが倒れて)戦闘が継続できないのですが,荷物を重視すると兵士を雇えないので戦力が弱くなる。
なので,どっちをどれだけ雇うのが最適なのか,それをプレイヤーにとって,ギリギリ分からないぐらいの感じにしたいんです。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/012.jpg) |
4Gamer:
荷物か,戦力かでプレイヤーが悩める状況を作りたいと。
畳部屋氏:
はい。もし,これが明らかに最適だとか,半々で雇えばいつもうまくいくとかになると面白くないですから。ほかにも,敵との関係だったり,敵と自分のパラメータの差だったりも,そういう(どっちつかずの)状況に,常になるようにしています。
では,それを具体的にどう調整するのかというと……やはり,エクセルシートであらゆるパターンを試し,そういう状況はこのゾーンだろう考えてパラメータを決定しています。
4Gamer:
そのエクセルが見てみたいです(笑)。
畳部屋氏:
いやあ,すごく汚いので……企業秘密とさせてください(笑)。
4Gamer:
なんとなく,ゲームとしての方向性は見えてきました。一方,サンドボックス系ゲームとして考えると,プレイヤーにとって自由すぎるがゆえに,逆に身動きが取れなくなる不自由だとか,不便だとかいった特徴があると思います。よくあるのが,まずはゲーム内の目的が分からないので,次のアクションが取れないというパターンですよね。
「歴史の終わり」のデモ版を少し触れてみたのですが,目的がどんどん追加されていくので,とりあえず,この目的のどれかに向かってみればいいのかなと,分かりやすく導線が張られているように思えました。
畳部屋氏:
それは,あえてやっています。まさにおっしゃるとおりで,私自身もサンドボックスを遊ぶのですが,ただ放り出されるのが好きじゃないんですよ。
4Gamer:
少し意外といいますか,もっと自由を重視しているのかと思いました。
畳部屋氏:
どちらかといえば,ある程度(目的を)絞ってほしいというか,絞ったうえで,そこから違うことをやってみようなのか,提案されたとおりにやろうなのかを決めたいんです。
だから,「歴史の終わり」も必ず目的があるようにしています。そのうえで,別のことも全部できますよという風にしているんです。
4Gamer:
なるほど。ところで,ゲーム全体の目的としては「世界の崩壊を解決する」ではなくて,「崩壊しないようバランスを取っていく」ということなんですよね。
畳部屋氏:
そうです。この崩壊がどういうものかというと,例えば,人間の精神が崩壊すると,無秩序になって国家を維持できなくなり,北斗の拳のような世界になってしまうといったものなんです。
つまり,ゲーム中の架空世界は,人間の精神が不安定になったり,緊張度が高まったりすると崩壊してしまうという設定になっているわけです。
4Gamer:
“世紀末”の世界にならないように,プレイヤーが頑張ると(笑)。では,どのような状況になると,崩壊へと向かっていくのでしょうか。
畳部屋氏:
例えば,一国の内側ですごく多くの文化を支配しているとか,街ごとの経済格差がすごく大きくなると,その国の「分断度」という値が上がります。実際にそうだと思いますが,1つの国がコンパクトで経済が均一だったら,わりと国はまとまりますが,巨大な帝国になるとすごく不安定になるものです。そして,この分断度が上がることで,「崩壊度」が上がるんです。
4Gamer:
自分の国を大きくしすぎて,制御できずに自壊してしまうみたいな。
畳部屋氏:
そんな感じですね。また,「憎悪度」というものもあります。これは戦争をしていくと,戦争相手のNPCから自国が嫌われて「印象値」がどんどん悪くなっていくのですが,そのマイナス印象値の総数が,世界の憎悪度になって反映されます。これも溜まっていくと崩壊度が上がってしまうんです。
4Gamer:
こっちは分かりやすく,行きつく先が全面戦争になりそうですね……。それは崩壊やむなしというか。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/018.jpg) |
畳部屋氏:
一方,この崩壊度を下げるためには,「寛容度」という値を溜める必要があります。これは,街に大学や図書館を作ると,教養が豊かになるという意味で寛容度を上げられるんですよ。
4Gamer:
文化レベルを上げて,戦争に至らないよう人々に寛大な心を学ばせる感じですかね。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/011.jpg) |
畳部屋氏:
ただ,人々が寛容になると,兵士になりたい人が減って,今度は戦争に弱くなったりするんです。
4Gamer:
あー,まさにこっちを立てれば,あっちが立たずという状況に……。
畳部屋氏:
そうです。先ほどのバランス調整の話につながりますが,そんなジレンマがあるんです。戦争をどんどん続けて,国を拡大し,文化的な施設を作らないでいると,崩壊度が上がり,世界が崩壊してゲームオーバーになります。
だからそうならないように,プレイヤーがいい感じに,世界のバランスを取らないといけないんです。
4Gamer:
いい感じ……ってすごく難しそうです(笑)。
畳部屋氏:
難しいと思います。例えば戦争が起こると,あるNPCが別のNPCを戦死させてしまいます。そうすると,その家族は殺した相手を憎んで,仇をとってやるという状態になります。その状態の人物は自分の王に,あの国と戦争しろと,激しく提案してくるので,争いを止めづらい状況になっていきます。
そうなると(戦争で)憎悪度は上がっていくし,戦争の結果として一国が拡大してしまうと分断度も上がる。このように,NPCを放っておくと,崩壊してしまいやすい世界を作っているんです。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/017.jpg) |
4Gamer:
そのどこかで,プレイヤーが介入しないといけないわけですね。
畳部屋氏:
そうなのですが,先ほどお話したクエスト(目的)を順次やっていくと,プレイヤーも基本的に国を作って,世界を制圧しろみたいな流れになるので,それをただ単に進めていくと,すぐに世界は崩壊してしまいます。
そうならないように,すぐに宣戦布告したがる臣下をなだめるのですが,あまり提案を拒否していると臣下からの印象が悪くなり,独立して自分の国を立てるとか言い出します。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/019.jpg) |
4Gamer:
NPCとの人間関係も大変だ……。
畳部屋氏:
ですから,この国とは同盟して,こっちの国とだけ戦争をするとか,臣下の意見も聞きつつ,いろいろなバランスをとりながら,世界をやりくりする……みたいなゲームです。
4Gamer:
なるほど。その崩壊度だったり,寛容度だったりなどの数値はゲーム中に見られるんですか。
畳部屋氏:
はい。グラフのような形で,崩壊度が上がっているとか,それがなんで上がっているのかとかも,グラフで見えるようにしています。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/023.jpg) |
4Gamer:
まさに世界のバランス調整なんですね(笑)。
畳部屋氏:
そうなんです。中間管理職の難しさみたいなものを楽しめます(笑)。
4Gamer:
崩壊しないようにバランスを取ることが目的ということは,おそらくゲームに明確な最終目的といったものがないと思うのですが,1回のプレイ時間やリプレイ性の部分はどうなのかが,気になります。
畳部屋氏:
今の段階でどこまで言っていいのか悩ましいのですが,テストプレイでは,初回で6〜7時間くらい遊んだら,プレイヤーが王になって,国が大きくなって世界が崩壊。1周目が終わるという感じでした。
その初回プレイで,最後は崩壊度が上がるばかりで止められなかったけど,どうしたら良かったんだろうと考えると思いますし,ゲームシステムも分かってきているはずです。
例えば,どういうタイミングで寛容度を上げる施設を作るべきなのか,技術開発ツリーもあるので,どの技術を先に取っていくべきなのか。いろいろとアイデアが浮かんでいることを想定して,ではその知識を持って2週目を始めようとなります。そうして,何回目かで世界征服が達成できるみたいなものを想定しています。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/014.jpg) |
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/015.jpg) |
4Gamer:
一応の目的,ゴールとして,世界の征服があるんですね。
畳部屋氏:
ゴールとは言っても,このゲームは過程を楽しんでほしいゲームなんです。シミュレーションゲームの太閤立志伝とかも,自由度はあるし,NPCもたくさんいるんですけど,あまり1人ひとりの人物がどういう人生を生きているのかは,そんなに分からないんです。自分のロールプレイ中心で,そこにあまりドラマ性を見せるような作りにはなっていないというか。
だけどこのゲームは,そういうのがわりと見えやすくなるように作っているつもりです。例えば酒場で誰かに話しかけたら,その人は最近何をしたのか,何を感じたのか,みたいなことを言ってくれるとか。あらかじめ,すごくたくさんのバリエーションが用意されていて,そのなかから一番合致するものを言うだけなんですけど。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/013.jpg) |
4Gamer:
誰と誰が結婚したみたいな情報が流れてきますよね。
畳部屋氏:
そうなんです。ほかにも「私の妻が敵国に所属している」みたいに言われたら気になるじゃないですか。その2人は戦うのか,どっちが勝つのかとか。
ほかにも夫が死亡しているNPCがいるんですが,よく見ると子供がいます。夫が死んだ日を見ると,どうも夫が死んだときには奥さんは妊娠していて,死んだあとに子供が生まれた,というのが年表から読み取れます。これは,その人物が戦闘に参加して戦死したために,そういう状況になっているわけです。
4Gamer:
自分がその戦闘に関わっていた……なんてこともありそうですね。
畳部屋氏:
ありえますね。そして,その小さい子供も,数年遊んでいたら成人します。そうなるとプレイヤーとしては,この子供がどういう人生を送っているのかと気になると思うんです。さらに,奥さんから「私の夫は死んでしまって,子供だけが残った」みたいなことを,主人公に言ってくれたりするかもしれません。
なので,必ずしもゴールを目指すことだけが楽しいわけではないし,バッドエンドになったから全部がおじゃんになったではなくて,それぞれの過程,その時々の偶然の組み合わせで,人物の面白い生きざまみたいなものを垣間見られる。そこが楽しめるゲームになってほしいなと思っているんです。
4Gamer:
主人公の行動で,思ってもいない展開もありそうです。バタフライエフェクトといいますか,自分の行動によってNPCの動きも変わってくるわけですよね。逆に,プレイヤーが完全に同じ行動を取った場合,同じように世界は進むのでしょうか。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/026.jpg) |
ランダム性があるので,それはありません。世界の初期生成にはランダムシードの数字を入れられるので,同じ数字を入れれば,同じ初期状態で始めることはできます。
ただ,例えばある人物は初期生成時に,わずかなお金を持っています。お金が少ないから交易をしましょうとなり,交易品を買います。そのときに,どの品物を何個買うかはランダム性があります。
木材を買うのか,陶器を買うのか。ちょっとしたことですが,それを買ったら,今度は移動して売って利益にする。でも,この利益がちょっと変わってしまいます。そういうのが蓄積していくと,今度はその人物が兵士を何人雇うか,1人2人しか雇えないのか,3人雇えるのかも変わってきます。
その結果,戦闘が発生したときに,勝ち負けが変わってきますし,それが変われば戦争の推移も変わるかもしれません。まさにバタフライエフェクトで,どんどん世界が変わっていくはずです。
4Gamer:
確かに,手持ちのお金が1円だけでも違ったら,どうなるか分からないですよね。
なんというか,NPCにそう(自由で)あってほしいというのは,プレイヤーの理想だと思うんです。NPCに対して起こしたプレイヤーのインタラクションが,何か世界に影響を及ぼしてほしい。メーカーも及ぼすとはいうけれど,それは思っていたものとは違うものがほとんどじゃないですか。でも,聞いているかぎり,本作はそうじゃないという印象を受けます。
畳部屋氏:
そうですね。自由度が高いとアピールするゲームはすごく多いですが,自分の思う自由度は実現できていない,みたいに不満に感じることがあります。
もちろん,私が1人で作れる範囲なので,肉厚ではないかもしれません。イベントのセリフがたくさんあるとか,NPCが1000人いるとかではなくて,ある程度コンパクトだし,骨組み,ゲームシステムの骨組みは自在に構造が変わっていくように作っています。
例えば,ある王が死んだら,その後継者が王になる。あるいは国が亡んだら,そこに所属していた臣下が散って,その人たちがまた別の活動をし始める。そういう自由度が本当にほしかったので,その実現に全振りしているゲームシステムを作ったというところがあります。
4Gamer:
先ほど,子供の成長の話を聞いて思ったのですが,時間の経過は主人公にどう影響するのでしょうか。要は寿命はあるのか,世代交代するのかみたいなことです。
畳部屋氏:
主人公は,120歳まで生きられる違う種族という設定で,900年からキャンペーンが始まって,1000年くらいになったら寿命を迎えたという1つのエンディングです。葬送のフリーレンとか,「ロストオデッセイ」の主人公とか,1人の人物の目で,NPC達の世代交代を見てほしいといった意図があったんです。
ですから,100年,1人の人間として生きていくのですが,プレイヤーは子供を作ったり,世代交代したりはしません。それは遊んでいる人の目ですから。
だけど,NPC達は3〜4世代と変わっていく。あいつの初代とは仲が良かったけど,その孫がこういうふうに人生を生きているのかみたいなことを見ることができます。
4Gamer:
ゲーム的には,基本的にその100年の物語を描く感じになるんですか。例えば,フリーモードのような,その後を続けていくことはできますか。
畳部屋氏:
いえ,100年経つとゲームは強制終了になります。これは内部的な技術上の問題がありまして,あまり過去のデータが蓄積しすぎると,ちょっと重くなってしまうので。
4Gamer:
確かに……NPCだけでも,系統図みたいなツリー状のデータが,恐ろしいことになりそうですね(笑)。
畳部屋氏:
そうなんですよ(苦笑)。
4Gamer:
しかし,先ほどコンパクトとおっしゃっていましたが,お聞きしているかぎりそうは思えないんです。逆に,どの部分がコンパクトになっているのでしょう?
畳部屋氏:
例えば武将数になるのですが,あの世界で同時に存在するのは100人ぐらいになります。三國志や信長の野望などは,おそらく1000〜2000人ぐらいだと思うのですが,そこからすると少ないですよね。
それよりも多くして,リアルタイムで同時に進行すると処理が追い付かないといったことがあるんです。逆に100人ぐらいだから,家族関係とか,友達の友達が別の国にいるとか,濃密な人間関係がどこにいても見られるので,それでいいかなと。
4Gamer:
人数を絞ったからこそ,一人ひとりを濃くできるといったこともありそうですね。
畳部屋氏:
そうです。なので,人物の数もコンパクトですし,戦闘もシンプルといえばシンプルで,キャラクターごとに必殺技が用意されているとかもありません。わりとシンプルに数と数で殴りあう感じです。
このように単純化し,あくまで人間関係から生まれる,それぞれの人たちの人生の生きざまだったり,立場が変わっていくことで,どういうドラマがあるのかというところだったりに注力しています。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/020.jpg) |
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/021.jpg) |
4Gamer:
小さな国の推移を見ているような感じですね。もっとも,三國志もソシャゲもそうですが,「レア(R)」カードはほとんど使わなくて,最高レア(キャラ)か,その1つ下くらいじゃないですか。いっぱいキャラがいればいいということでもないとは思います。
畳部屋氏:
それは,そうですね(笑)。
4Gamer:
それこそ,強い武将か,いっそのこと弱い武将で下剋上を狙うとか。あっても,思い入れがあったり,少ないとは思いますが自分に縁のあったりする武将ではないかと。
畳部屋氏:
やっぱり三國志や信長は,歴史を再現しないといけないという使命があるじゃないですか。だから,三國志を見ると,役職などは実際の中国に沿った複雑なものがあって,この人物はその役職だったから,システム上は入れないといけない。必ずしも,その役職全部がゲームに効果的に効いているかというと,そうでもないじゃないですか。
だから,そういうのは私のゲームでは歴史に沿う必要がないですから,バッサリとカットできるんです。
4Gamer:
あと,先ほど触ってみて,主人公が装備を購入したらすぐに重量オーバーになって,移動していたら食料があっという間になくなってみたいに,世界を動かす(主人公が移動する)と起こる,リスクみたいなものも感じられました。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/009.jpg) |
畳部屋氏:
主に初期のころはそうですね。そこから,荷物運びの傭兵を雇うと荷物がたくさん運べるようになりますし,食料も確保できるようになります。ある程度,地位があって,領地とかを手に入れると税収が入ってくるので,そのお金を使って,より大きな別のことができるとかもあります。
ただ,食料がこんなにすぐ消えるというのが気づきにくいというのは,テストプレイの方々からも言われるんです(苦笑)。
4Gamer:
そうですよね(笑)。
畳部屋氏:
そこは,もう少しチュートリアルを厚くするとか,調整したいと思っています。
- 関連タイトル:
 歴史の終わり
歴史の終わり
- この記事のURL:
キーワード
(C)2024 Tatamibeya All Rights Reserved.



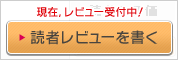
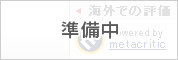





![[インタビュー]崩壊ギリギリのバランスで世界が動くSLG「歴史の終わり」の制作者である畳部屋氏に,ゲーム内容や個人制作の苦労を聞いた](/games/935/G093580/20250812045/TN/024.jpg)