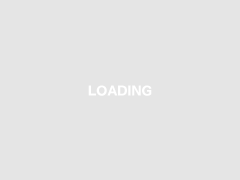イベント
学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]
しかし現在では,推し活文化が日常に浸透するほどに,ポジティブなものとして受け入れられるようになった。そうした文化の中心には“ファンダム(熱心なファン集団)”の存在があり,彼ら彼女らは単なる消費者から,創造的な文化の担い手として認識されつつある。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/001.jpg) |
「CEDEC 2025」で行われた岡部大介氏によるセッション「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」では,この現象の中心である“ファンダム”が学術的視点から解き明かされた。
コミュニティの中で人々はどのように学び,創造し,生き生きと楽しんでいるのか――。その性質と実践の数々が語られた本セッションのレポートをお届けしよう。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/002.jpg) |
ファンダムにおける“交歓”経済
軽やかだけどディープに遊んでいる実践に迫る
セッションの前半では,ファンダムが「軽やかだけどディープに遊んでいる実践」の数々が紹介された。
その1つが,映画「アバター」で使用される架空言語「ナヴィ語」を,ファンが自発的に解析し,体系化した事例だ。
これは,言語学者が使うような手法を用い,耳で聞いた音を世界標準の発音記号に当てはめるという活動である。解析された「ナヴィ語」はWeb上の「Learn Na'vi」にまとめられ,YouTubeでは言語学的な収集方法や発音記号への当てはめ方が動画で共有された。
面白いのは,この言語解析が誰かに頼まれたわけでもなければ,運営側が仕掛けたものでもないという点だ。むしろ,公式が“ある程度ほったらかしにしてくれている”ことで,かえってファンの楽しみが深まった事例であり,このような現象はファンダムの中ではよく見られるのだという。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/003.jpg) |
日本における同人誌,二次創作の土壌でも,こうした「軽やかだけどディープに遊んでいる実践」が見られると,岡部氏は話す。
「大奥」「きのう何食べた?」を手がける漫画家 よしながふみ氏は,同人誌即売会を“学説発表の場”になぞらえ,それぞれが作品解釈を持ち寄り,反応を見ながらアップデートしていく場として捉えているそうだ。
また,認知科学者である久保氏の考察によると,腐女子の活動は「原作テクストに描かれていない不自然な点や余白を見出し,疑問の解消を試みる実践」であるとされ,これは学術用語で「アブダクション(仮説推論)」と呼ばれる思考法そのものではないかと論じられている。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/004.jpg) |
では,このアブダクションとはどのようなものなのか。岡部氏は「アンパンマン」を例にそのプロセスを説明した。例えば,「バイキンマンは毎回負けるのに,なぜアンパンマンのパトロール経路で必ず悪さをするのか」という疑問が生まれたとする。
しかし,ここで生まれた「なぜ?」には明確な答えはなく,想像をめぐらせるほかない。そうした引っ掛かりや,原作テクストに描かれていない余白は,腐女子が面白さを感じるポイントであり,何かを解消したい欲求に駆られるトリガーとなる。
そこで,疑問の解消を試みる実践として「バイキンマンはアンパンマンに振り向いてほしい。愛情の裏返しからの行動では?」という仮説が立てられる。
だがここで,「愛と勇気だけが友達のアンパンマンが,バイキンマンの愛に気づかないことがあるのだろうか?」と,新たな疑問が生まれてしまう。
それを解消する説として「アンパンマンはバイキンマンを転がしているのでは」と,さらなる問いに発展する……このように弁証法的に論が構築されていくのが,アブダクションである。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/005.jpg) |
規模の大きいファンダムとして挙げられたのは,「ハリー・ポッター」のファンコミュニティ“ダンブルドア軍団”だ。このファンダムで行われているのは,シリーズに登場する物体移動の呪文である「アクシオ」を,ポジティブな行動に結びつけ,社会に貢献する実践である。
その活動として挙げられるのが,「アクシオ ブックドライブ」だ。
これは,自宅にある価値ある書籍を,蔵書数の少ない公民館や図書館,新設の施設にアクシオ(寄贈)するというもの。
社会貢献に燃える志の高さが支える活動ともとれるが,岡部氏は「ファンからすれば,オンライン上で『アクシオ!』と言いたい」欲求と快楽が根底にあると話す。
「天空の城ラピュタ」の放送時に,SNS上でこぞって「バルス」を唱える現象と似たものだそうだ。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/006.jpg) |
ファンとしての活動が社会参加につながる事例は,韓国の音楽グループBTSのファンダム“ARMY”にも見られる。
BTSのメンバーが選挙の投票済みマークをSNSに投稿したことをきっかけに,日本のARMYによる“投票認証ショットチャレンジ”が行われた。このファン活動は参議院選挙に合わせて実施され,投票認証マークをデザインしたタトゥーシールと,“Go Vote”のリーフレットが配布された。
これは,BTSのメンバーと同じ体験をしたいという欲望が原動力であり,選挙への参加を促す活動に加わりたいという欲求から生まれた実践であると,氏は分析する。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/007.jpg) |
コスプレコミュニティにおける実践として,研究室に所属する生徒の事例も紹介された。
その生徒は「進撃の巨人」のコスプレをするべく,立体機動装置の小道具を製作していたのだが,その再現に苦労していたそうだ。そこに,あるファンによって「ダイソーの子供向け太鼓とライオンボードを組み合わせる画期的な方法」が共有されると,解決策が見つかったと興奮していたという。
ユニークなのは,この生徒のその後の行動だ。この情報によって製作時間を短縮できた生徒は,その時間を塗装のクオリティアップに充て,成果をSNSで共有する循環が生まれたのである。
これはコスプレコミュニティによく見られるものだそうで,「誰かからの何気ないギブをありがたくゲットしつつ,そのギブされたものを自分のものに生かし,また誰かにギブする」連鎖がたびたび生まれるという。また,こうした循環がコミュニティ全体の創造性を高めていくと,岡部氏は話していた。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/008.jpg) |
フィールドワークで得られる内側からの視点
ファンダムの文化を理解するにあたり,岡部氏はフィールドワークを主な手法としているという。フィールドワークとは,調査対象のコミュニティに実際に入り込み,彼らと共に過ごしながら,その文化や実践を理解しようとする研究手法である。
岡部氏は,フィールドワークの面白さは「見えていたけど気づいていないこと(Seen but not noticed)の概念化」「最初は不合理に見える他者の合理性を理解する修行」「あたりまえに受け入れている常識を相対化」の3つに集約されていると話す。
「見えていたけど気づいていないこと(Seen but not noticed)の概念化」とは,網膜には映っていてなんとなく存在は知っているが,名付けがされていないがゆえに認識されていないものを明らかにすることだ。みうらじゅん氏によって名付けられた「マイブーム」や「ゆるキャラ」が,これに当たる。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/009.jpg) |
「最初は不合理に見える他者の合理性を理解する修行」「あたりまえに受け入れている常識を相対化」の例として,コスプレイヤーを観察したケースが紹介される。
あるコスプレイヤーを定点観測した際,3週間かけて作ったウィッグや衣装を,撮影後すぐに捨ててしまう行動が見られたそうだ。
調査者側からすれば,「寝食を忘れて作ったのになぜ?」と,その行動は不合理なものとして映るだろう。しかし,それはあくまで調査者側の常識から見た不合理さであり,コスプレイヤーである彼女にとっては,合理性のある行動だったのかもしれない。
その合理性を理解するには,観察のなかで調査者自身の常識を相対化し,対象者の世界観を内側から理解する試みが必要となる。フィールドワークはその繰り返しであり,修行のようなものだと岡部氏は述べた。
また,フィールドワークとは「対象者の日常生活世界を一緒に探索しながら,調査者側がその世界の中の住民として変化する」ことでもあるという。フィールドワークは時間がかかり,成果が見えにくい方法かもしれない。
しかし,ファンダムのような複雑で創造的な文化現象を理解するには,この「内側からの視点」が不可欠であり,単なる観察を超えて,研究者自身が文化の一部となることで初めて見えてくる世界があると,氏は強調していた。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/010.jpg) |
ファンダムと企業の共創的関係を目指して
ファンダムは欲望に忠実に動き,ときにその熱量がコミュニティの維持や,ファン同士の相互扶助に,意図せず接続することがある。公式からの働きかけがなくとも,ファンが自ら行動し,コンテンツの輪を広げていくというのは,これまでに挙げられた事例からも明らかだ。
そうしたファンダムの自走によって生まれるメリットは,決して小さくはなく,プロモーションにおいてプラスに働くケースもある。とはいえ,企業側からすれば“なにをしてもOK”とするのは現実的に難しく,ファンダムをどの程度自走させるべきか,頭を悩ませている企業も多いのではないだろうか。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/011.jpg) |
こういった現状を鑑み,岡部氏は「ガチガチに規制するとその界隈が一気に収縮していく」とし,よりよい関係を構築するのであれば,「自走するファンダムに対して駄目なものは駄目としつつ,ほどよくコントロールを手放す」ことが大切であると説く。
また,ファンダムと企業の関係を考える一助として,イヴァン・イリイチ氏の「コンヴィヴィアリティ」という概念を提示する。これは,「それぞれの人のあいだの自律的で創造的な交わりと,それぞれの人の環境との同様の交わり」を意味し,日本語では「共愉」と訳される。
中の人がフィールドワーカーにならないまでも,そのスタンスで接すれば,ファンダムとの共愉的な関係に近づけると岡部氏は述べ,「ファンダムとコンヴィヴィアルな関係をどのように実現するか,それを模索するのも面白いと思います」ともコメントしていた。
ファンダムを単なる消費者として見るのではなく,ともに文化を創造する存在として捉える。それこそがファンダムの創造性を解放し,より豊かな文化を生む近道となるのかもしれない。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / 学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/012.jpg) |
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 講演/シンポジウム
講演/シンポジウム - この記事のURL:


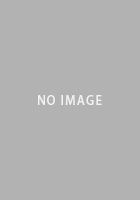
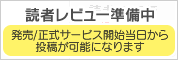
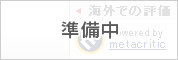






![学術的視点で迫るファンダムの生態。「共創としての『推し活』:ファンダム・コミュニティのフィールドワーク」レポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250725037/TN/013.jpg)